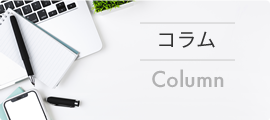業績が悪化した会社を立て直した経営者の話しを聞きますと、多くの方が「数値をオープン」にし、社員全員で危機感を共有したことが、成功の要因だったと語ります。
日本航空(JAL)の再建に尽力した稲盛和夫氏も、会社更生法が適用されても危機感の薄い社内の雰囲気に対し、コストを可視化する取り組み(アメーバ経営)によって、当事者意識を植え付けていったのは有名な話しです。
ところが、数字という目標やノルマがマイナスの効果を生んでしまう場合があります。
相模屋食品のケースがそうでした…
数字に出ない強みが評価されない
相模屋食品と聞いて、「もちろん知ってますよ」という方は少ないと思います。
でも、ガンダムの「さザクとうふ」を作った豆腐屋さんと言えば、たいていの方は、「ザクとうふの会社ね」と思い出されることでしょう。
その相模屋食品さんは、全国の豆腐屋さんをM&Aで再建してきた会社でもあります。
業績が傾きはじめた豆腐屋さんは、経営者が生産効率やコストダウンなど数値目標を徹底するようになります。
すると…、
現場は数値目標を達成するために、おいしい豆腐づくりを捨てて、数値目標を達成するために「白い塊」を作るようになります。
おいしくない「白い塊」では、お客さんが離れてしまい、負のループが加速することになります。
「このやり方は間違っている」と思っていても、数値目標がある限り白い塊を作り続けるしかないのです。
相模屋食品の鳥越社長はそんな負のループを断ち切るため数値目標を撤廃したのです。
「かつてお客様に喜ばれていた美味しい豆腐をもう一度作ろう」
「やらない方がいいと思っていたことは全部やめよう」
こうやって、歩留まりやコストといった数値目標をやめ、現場の人の気持ちに再び火を点け、復活へと進んで行ったのです。
管理しやすい数値目標だけで判断してしまうと、自社の強みが薄れてしまう良い例えだと思います。
極端な利益追求をしない
日本航空(JAL)の再建で活用された「アメーバ経営」は、従業員が数字を意識し主体的に経営に参加するように、会社を細かい小集団に分けて、その小集団で利益を上げるように自分達で業務改善を行うものでした。
それほど、かつての日本航空では現場のコスト意識がなかったという事です。
ところが
中小企業で「アメーバ経営」を取り入れてみようとすると、本来の意図から外れ、自分の小集団だけが利益を追求する
間違った行動を取るようになります。
自分の小集団で扱っている製品やサービスを他の小集団に移管するのが難しくなるのです。
※自分の小集団の利益が縮小や減少したくないから…です。
現場の人が意図を理解しないまま、極端な利益追求やコスト意識を持つようになると、会社の中で、無意味な縄張り意識が生まれて、組織が硬直してしまいます。
そのような意味で、相模屋食品さんは現場にコスト意識を持たせていません。
※ただし、経営者はグループ全体で数値を把握しているそうです。
営業マンにも数値は求めない
豆腐やタマゴ、もやしは、スーパーの特売で扱われる商品です。
どこのお店で買っても同じで価格だけが差別化のポイントとなっていました。
ところが、相模屋食品さんは
「ザクとうふ」や「うにのようなとうふ」
といった個性で勝負しています。
やみくもに売上を追求していないのです。
そういう背景から、とうふを特売商品として見ていないお店とは付き合わないそうです。
なので、営業マンにもノルマがないそうです。
売上げを求める営業マンが目標とかノルマがなくて、どうして会社が成長できるのか不思議に思いました。
けれども
営業マンが求めるのは、薄い利益のとうふではなく、一緒に売り場をつくることとする方針から、相模屋食品と扱っているお店が共存共栄している様子が伺えます。
相模屋食品のケースはレアケースかもしれません。
けれども数値の把握以外にも着目する必要があると気づかせてくれます。
生産性向上とか、労働分配率とか数値で把握することも大事ですが、数値で現れない自社の強みを改めて見直してみるのもいいのかもしれません。
笑顔創造研究所は、みなさまの笑顔と地域経済を応援しています。