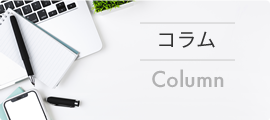最近は、秋がほとんどないでよね。
夏がずっと続いて、突然冬になる感じです。
この気候変動は、日本だけでなく世界の経済社会に大きな影響を及ぼす問題となってます。
こうした中で、カーボンニュートラルへの対応が急務とされていても、中小企業では、資金面の問題などで具体的な取り組みを進めることが困難である場合が多いです。
身近なところでは、2027年末をもって蛍光灯の製造・輸出入が禁止されますが、それどころでない中小企業も多いと聞きます。
持続可能性を高めると言われても…
エネルギー価格や人件費の高騰により収益率が落ちているのに、2050年カーボンニュートラル社会の実現が重要だと言われても、
あるいは
中小企業の脱炭素化は喫緊の課題だと説明されても、
その前に会社の経営の方が大事だと言い切る方は多いと思います。
取引先の大手企業から脱炭素化への対策が不十分だから、取引きを中止されたなんてニュースは報道されてないので、どうしても省エネまで手が回らなくなってしまいがちです。
一方、脱炭素化に取り組めるのは、余裕のある中堅企業が中心ですが、その取り組みが評価されて企業イメージ向上や優秀な人材の確保にも繋っています。
またエネルギーの安定供給の面でも省エネは重要な問題です。
そのような背景もあって、地域経済を支える「地方銀行」が、省エネ支援の役割を求められるようになりました。
脱炭素支援は、なぜ地方銀行なのか
中堅ではない、ごく普通の中小企業では、省エネ機器の導入や更新だけでなく、省エネ診断などを自力で実施するには限界があります。
経営者が省エネ投資のメリットを十分に理解していないこともありますが、省エネ設備への投資は初期費用が高額となるケースもあるので、補助金や金融支援がないと着手するのに躊躇しがちです。
また、補助金活用を考えていてもどの支援策がいいのか把握が難しく、エネルギー管理や省エネに精通した担当者が社内にいない場合がほとんどです。
そこで、中小企業が気軽に相談でき、信頼関係のあるパートナーである地域密着型の地方銀行に白羽の矢が立ったという訳です。
(既に昨年の7月から、省エネ・地域パートナーシップとして支援体制は始まっています)
来年からは、中小企業の省エネを支援するために、地方銀行に対して省エネ支援計画の公表を促すことになりました。
※省エネ支援計画の内容
金融機関が作成する計画には、以下の内容が含まれる予定です。
・省エネ支援件数の目標値
・行員への省エネ研修の計画
・各支店への専任担当者の配置想定
この計画は、各銀行がホームページで開示するほか、経済産業省も一覧として公開する予定です。
公表は任意としていますが、省エネ・地域パートナーシップの実行者リストに載らなければ、省エネ支援に後ろ向きな金融機関として判断される可能性もあるので、必ず省エネ支援計画については各金融機関が公表するでしょう。
2026年度から省エネ支援に熱心な金融機関を表彰する制度を導入する予定なので、これからは省エネに対して後回しではいられなくなります。
具体的に何を求められるか?
賃上げをしなければならないし、生産性向上やDX化も必要で、事業承継や人材確保とやることが多岐にわたる中でも、省エネ向けて取り組む必要が出てきました。
まだ何も着手していない事業者の場合は、省エネ診断を勧められることになると思います。
大きな工場や、保有トラックが200台以上の事業者には、省エネ法の規制がかかっていました。
これからは、どの事業者にも省エネの目標値をもたされるようになるかもしれません。
冷暖房設備やボイラーだけでなく、既存設備がどれだけCO2排出しているか把握することから求められるでしょう。
その上で、エネルギー効率の改善のために省エネ設備の導入や更新を勧められることになります。
場合によっては、補助金活用であったり、省エネ投資に特化した低金利融資商品を案内されることでしょう。
取り組まなければならない事が沢山ありすぎて、省エネまで手が回らないと言いたいところですが、最近の異常気象や平均気温の上昇を経験してしまうと、見過ごすことはできない状況です。
暑いこの時期だからこそ、省エネについて熟考してみましょう。
笑顔創造研究所は、みなさまの笑顔と地域経済を応援しています。