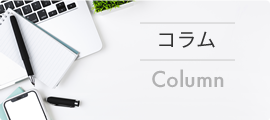中小企業企における最も深刻な課題の一つは「人材の確保」です。
大企業に比べてブランド力や給与水準で劣るケースが多く、慢性的な人手不足に悩まされています…。
今までの採用活動は、
「どれだけ優秀な人材を外部から連れてくるか?」という中途採用に焦点を当てがちでした。
しかし、採用コストの高騰と、採用してもすぐに辞めてしまうという「高い離職率」を目の当たりにし、多くの企業が解決策を探していますが、今までの「採用至上主義」から「定着率向上」へと採用の軸足を移す企業が成果をあげてきています。
つまり、今いる社員を辞めさせない事がとても重要になったのです。
もっと言えば、採用した人材が1年以内に離職しないことがとてもカギとなるように変化してきた訳です。
離職がもたらす隠れたコスト
採用した人材が定着しない場合、採用に費やしたコストが無駄になってしまいます。
この離職によって発生する隠れたコストを徹底して認識しないと、いつまで経っても採用至上主義のままとなります。
具体的には、以下のようなコストです。
〇再び求人を出して、面接など採用活動を行うことで発生するコスト
〇採用した人を教育する指導者が他の業務が行えたであろうコスト
〇生産性が一時的に下がるのを残業等でカバーするコスト
〇人員不足による業務負担増による社員の疲弊や士気低下をカバーするためのコスト
これらの隠れたコストまで意識して人材育成をしなければ、「穴を埋めるための急募」が続いて組織力の低下だけでなく、成長力の源泉が喪失となってしまいます。
政府が生産性向上を求めていますが、何もDXだけが解決策ではありません。
早期離職が増えるほど、隠れたコストが発生するので、生産性は下がります。
逆に、定着率が高い企業ほど、社員の習熟度が上がり、結果として生産性の向上の効果が発揮できる訳です。
労働条件の改善は一時しのぎ
今いる社員を辞めさせないために、給与面や年間休日といった労働条件を改善することを勧める人もいますが、一時的には効果がありますが、その効果は長くは続きません。
(これは、ハーズバーグ先生の「衛生的要因」とか「動機付け要因」でご存知の方が多いことと思います)
定着率向上で重要なのは、「明確な育成計画」と「人材育成」がカギであると感じています。
失敗を許してもらえる組織が重要だ…とか案内したことがありましたが、明確な育成計画を持っていない企業が多いことに正直驚きました。
(育成計画が明確でないので、「何を」もしくは「どこを」評価するのか不明瞭でやりがいを感じられない職場となっている事に案外気づいてないと感じてます)
人材育成とか教育については、現場の社員・スタッフに対して行うものというより、管理職や経営幹部が今の時代にあった組織とはどんなものか、知識をアップデートする研修に注力すべきです。
仕事ができる人が管理職になった場合、「部下がどうして仕事が遅いのか」(自分が出来て当たり前なので)部下ができない理由を理解することが難しかったりします。
また、傾聴をはじめとした今の組織に必要なコミュニケーションスキルが不十分であることが多く、現場の困りごとが上がってこない組織になっている点を早期に改善する必要があるのに、「職場の仲がいいのですよ」なんて呑気に話す社長を見て、流石に手の施しようが無いと落胆したことが有りました。
心理的安全性が必要とか言われますが、今いる社員を辞めさせないためには、経営者や幹部(上司)の言動が組織の空気を大きく左右することに注意を払うべきです。
そのための社員教育を徹底していきませんか?
あばたもえくぼ
かつて勤務していた職場に全く仕事ができない人がいて、何故 そんな人が長く勤務できるのか不思議で仕方がありませんでした。
そんな疑問に対して、その時の上役から「あばたもえくぼ」なんだよと、諭されたのですが、当時は社会人になったばかりで、さっぱり理解ができませんでした。
でも困った時に、その人に聞けば何でも教えてくれました。
いつもニコニコしていて、褒めるのが上手な人でした。
今思うと、ムードメーカーでギスギスしがちな職場の中では必要な人材だったと分かります。
今いる社員を辞めさせないために、コミュニケーション能力の高い人が職場にいるでしょうか?
そのような人がいない場合は、自分の業務が社会や会社に貢献しているのを実感を持てるような仕掛けを持ちましょう。
会社がどこを目指しているのかビジョンを明確にすることでもいいですし、「働きがい(貢献感・成長感)」を提供できる職場環境でもいいです。
今いる写真の定着率を高めることなく採用を増やしても意味がありません。
定着率が高まれば採用コストは減り、最終的には組織力が上がり、企業は自然と魅力的になっていきます。
「定着率重視」への転換が未だの会社の方はこれを機会に、改革に着手していきましょう。
その取り組みは、確実に企業の未来を豊かにしていくはずです。
笑顔創造研究所は、みなさまの笑顔と地域経済を応援しています。