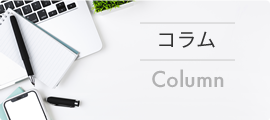単なる「悪ふざけ」では済まされない
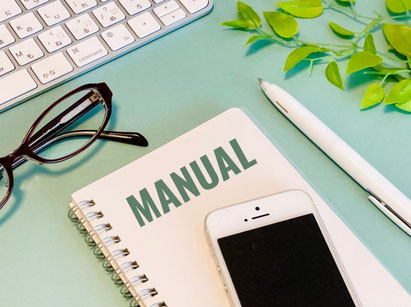
またしても、山形県の回転すし店で一部顧客による「迷惑行為」が行われました。
2023年1月末、別のチェーン店で「しょうゆ差し」を直接なめた少年の動画が拡散され、大問題になりました。
この少年に約6700万円の損害賠償を求めて訴訟された…というニュースを見ていたはずです。
それでも、学生服を着用した女性はしょうゆ差しから直接口に流し込む様子を撮影していたのです。
その様子を店員は見ていなかったのか?
それとも、どう対処していいのか迷っていたのか?
今回は、「 マニュアル信仰の落とし穴 」についてお届けします
多くの中小企業(特に製造業)において、問題が発生した際の最初の対応は「マニュアルの改訂と徹底」です。
従業員に対して手順書を読み込ませ、署名を取り、周知徹底を図ります。
取引先から、そのように求められます。
マニュアルは、「予測可能な事態」に対する「標準化された手順」を定義するもので、その目的は「安全かつ円滑な運営」です。
しかし、回転すし店での迷惑行為はマニュアルや衛生管理手順の範疇を超えたもので、隠れて迷惑行為を行うケースなど、発生そのものをマニュアルで防ぐことは非常に難しいです。
仮に、マニュアルとして迷惑行為を発見した場合に
「客に注意する」「見かけたら止める」
という指示があったとしても従業員(多くがパートの方)個人が
「争いになるのは面倒だ」
「クレーム化するかもしれない」
「対応ミスでトラブルになるのは嫌だ」
といった不安を持つのは当然で、そこまで責任をとりたくない…と、現場で尻込みしてしまうことは十分にあり得ることです。
マニュアルのせいで「思考停止」
中小企業で何か問題が発生するとマニュアルもしくは手引きが細かくなっていきます。
内容が細かくなればなるほど「マニュアル通りにやること」が目的化することになります。
何のためにマニュアルに記載された内容を行う必要があるのか、目的を理解できない人が沢山でてきても、マニュアルに通りに作業すれば問題が発生しないと勘違いします。
(目的を理解していないため)マニュアルに記載されていない事象が発生すると思考停止となります。
上司にあたる方の指示や、ベテラン社員のアドバイスがないと臨機応変に対応できなくなるのです。
※飲食サービス業の場合であれば、サービスマニュアルを徹底しても、発生後の警察への通報や清掃ぐらいしか行うことはできず、「迷惑行為の抑止力」や「損害の回収」にマニュアルは寄与しないのです。
まさに、マニュアル信仰の落とし穴がここにあります。
もし、回転すし店等の飲食サービス業の目的が「善良な顧客に快適にサービスを提供する」であれば、迷惑行為をする少数の顧客に対して、毅然とした態度で臨んで良いという判断と行動が可能となります。
毅然とした態度・対応は、「店を守る」だけでなく、「良いお客様の快適な環境を守る」ための「正当な対応」に繋がっていきます。
大切なのは、マニュアルを守ることだけでなく、何を目的に判断して、行動するという事になります。
正解のない状況下での訓練
これからは、カスハラ対策が義務化されます。
マニュアルは、起こってほしくない事態を想定して「事後対応」を規定するものです。
カスハラ等の問題行為に対しては、単なる業務マニュアルの遵守では対応できない事案も出てきます。
マニュアル想定外の事案が発生した場合、従業員は臨機応変に判断する技量が求められます。
そのためにも、正解のない状況下での訓練が必要となってきます。
多くの場合は、トラブルが起こってから事例を共有することが多いですが、カスハラはある程度はパターンが想定することができるので、想定外が発生する懸念があっても事前に対応策を準備することができます。
「今から行くから待ってろ」
「インターネットでさらしてやる」
と暴言や脅迫をしてくるケース
過度な要求を求めてきたり、
店員に土下座を要求するなど
不当な要求を求めるケース
クレームの長電話や
長時間の説教や拘束をするケース
これらのトラブルは大まかなパターンがあるので、そのパターンに対応した応変を訓練することができる訳です。
弁護士が対応すると説明すれば、長時間のクレームに対処しなくていいケースもありますし、無理難題な要求に対して
威力業務妨害として拒絶することもできる訳です。
正解のない中であっても、ある程度の訓練は可能であるのです。
私が、実際に体験したトラブルでは強面の方が鬼の形相で入口に立っていて、
「要件をお伺いします」と言った瞬間に
「何回も言わせるな」って騒ぎ出しました。
当時の上司は、無責任に「殴られたら警察呼べたのに」って言って腹が立ちましたが、警察に相談しにいったら、法的手段の知識と対応策を教授してもらい、安堵したことがありました。
さて、カスハラに限らず、何かエラーや問題が発生するのは、教育カリキュラムの不備であったり作業環境のエラーといった構造的な問題である場合が多いです。
そのような問題があるのに、現場から問題があがってこないのは、エラーを個人の責任とする組織文化があるからかもしれません。
そのような組織で「マニュアルの徹底」を図っても、効果が出ないのは明白です。
むしろ、例外的な対応が発生しても、「どう判断すればいいのか」判断できる現場の知恵袋(もしくは改善提案)を共有する組織でなければなりません。
現場での不備や非効率な点に気づいた際、それを組織へ上げる仕組みはありますか?
エラーを「学びの機会」に変える組織文化を醸成して、マニュアル信仰からいち早く脱却していきましょう。
笑顔創造研究所は、みなさまの笑顔と地域経済を応援しています。