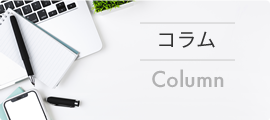今は違うかもしれませんが、学校では、常に先輩の方が上の立場で、上下関係がハッキリしていました。
先輩が間違ったことを言っていても、「昔は間違っている」なんて指摘はできませんでした…。
稀に、スポーツ万能な新入生が加入すると、先輩に気を使いながらプレーしなければならないジレンマが有ったほどです。
その新入生がチームの絶対的な存在であると認められると、あまり気を使わなくなりますが、多くの場合「上下関係」の呪縛が付きまといました。
しかし、社会人になると、その「上下関係」の立場が変わってしまう時があります。
そうです、「年上の部下」であったり、「年下の上司」というケースです。
残念ながら、「年上の部下」が職場の雰囲気を悪くするケースが多く、しっかりと対処していかないと仕事のできる「年下の上司」が会社から離れてしまうことになりかねません。
「年上の部下」の多くは、それまでの学校生活のなごりがあるので、仕事の人間関係において、「自分より経験も少ないのに年下が上司面しやがって…」と卑屈な態度に出てしまうのはある意味仕方がないことかもしれません。
何が正しい対処法であるか?
年上の部下が業務命令をきちんとこなさず、馬鹿にした態度をとる場合、状況を改善するためによく言われるのは事実を淡々と伝えることだとされます。
いつ、どのような業務命令に対し、どのような対応(不履行、遅延など)をしたのか、詳細に記録しておき、客観的な事実に基づいて対処するという方法です。
馬鹿にしたような発言、態度、ため息は確かに問題はありますが、そこに焦点をあてるのでなく、業務をきちんと処理しないことに責任を取ってもらうという対処方法です。
「年上の部下」の方に対して、感情的にならずに、業務の指示や目的が正確に伝わっていたか、締め切りが〇日だったのに何故提出が遅れているのか、事実ベースで確認して、未対応のものには責任をもって実行してもらうというものです。
※ただし、非常に難易度は高いです…。
業務をきちんと処理しているならば、問題ないのですが、対処していないのに悪態をつく場合は、これは、部下によるパワハラに該当する場合もあるので、会社としてハラスメントの対処をしないといけなくなります。
また、年上であることに敬意を持ちながら、年上部下に「教えを乞う」のも一つの対応策と言われています。
しかし、このやり方の問題点は、正しいこと(こう改善したら処理が早くなる、手書きでない方がミスは出ない等)、
真正面にそのまま伝えても、関係が構築できない段階では、全く聞き耳をもってもらえない場合があるので、全てのパターンで通用するやり方ではない手法です。
つまり、これをすれば解決できるという安直なやり方は無く、結局はコミュニケーション力にかかっているという事になります。
一番の問題点は会社にある
さて、「年上の部下」が悪態をとったり、「年下の上司」が悩みを抱え込むのは、会社が「あるべき姿」を言語化していないことが大きな問題です。
もっと具体的に言えば、「リーダー等になる人は、このスキルがある人」という言語化がされてないのです。
入社〇年ぐらいたったから、業務成績がよかったから、こんな基準でリーダーを任命していては、どうリーダーとして活動していいのか分からないのです。
会社で「どう指導して欲しいのか」あるべきリーダーの姿が言語化できていないので、任命された方は、「何をすればいいのか」理解できずに、行動が空回りすることに繋がっています。
例えば、プレイングマネージャーを
・全体業務を把握した上で、個々の進捗を管理し、遅れた作業をサポートする
・レベルアップにつながる技術指導を行う
・指導は、傾聴する姿勢で行う
と、言語化した場合なら「なぜ、遅れているんだ」とは叱責できません。
どれだけの業務を抱えているのか、把握もせずに原因を特定しようとしているからです。
また、現状を把握する際の行動が、傾聴姿勢になっていないと指摘することができます。
同じように、年上部下に対しても期待する役割を言語化しなければなりません。
他のスタッフとの間に入って、
調整役となり、リーダーの目の届かない
部分を下支えする
経験を活かして改善点を提案してもいいが
誰もが見ている中で批判する行動は慎む
たったこれだけであっても、言語化していれば、馬鹿にしたような発言、態度、ため息を取る行動は、慎むべきであると会社が指導できます。
何もかも、言語化してルールでがんじがらめにしようという意味ではありません。
「言わなくても分かるでしょう…」という曖昧な認識を排除するという趣旨です。
業務遂行する上で、どう行動すべきか、未だ言語化ができていない会社は、これを機会に言語化に取り組みましょう。
笑顔創造研究所は、みなさまの笑顔と地域経済を応援しています。